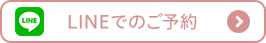目次
養育費とは
養育費とは、お子さんの監護に関する費用のことで、お子さんが自立するまでに必要となる費用です。
衣食住の費用、教育費、医療費、娯楽費など、お子さんが自立するまでに必要となるすべての費用が養育費にあたります。
いつまで養育費を支払ってもらえるかという期間の終期としては、成人する20歳が最も多く、その他には、高校を卒業する18歳までや、大学を卒業する22歳までといったケースが一般的です。
養育費の算定方法
では、実際、養育費はいくら支払ってもらえるのでしょうか。
養育費の金額は、負担する夫側の経済力や生活水準によって変わってきます。
基本的には、養育費は、夫と妻双方の収入に応じて算定されます。
財産分与や慰謝料は一括で支払うのが原則ですが、養育費は通常定期的に負担していきます。
目安として、裁判所が算定表と呼ばれる早見表を作成しています。
算定表のリンク
「裁判所 養育費算定表」と検索すれば、すぐに早見表を見ることができます。
お子さんの人数と年齢から、あてはまる算定表を選択します。
次に、双方の収入を見ていきます。給与所得者であれば、去年の源泉徴収票の「支払総額」(控除されていない金額)を年収としてみます。自営業者であれば、去年の確定申告書の「課税される所得金額」を年収としてみます。
※当サイトの養育費シミュレーションはこちら>>
裁判所の離婚調停では、この算定表を基本として養育費の額が決まっていきます。
お子さんが小さい場合には、養育費の支払は非常に長期に及ぶもので、総額となると相当な金額となります。お子さんを育てるために必要となるものですから、慎重に検討した上で、養育費の金額を決めることが望ましいです。
養育費の増額や減額
いったん養育費の金額を決めてしまうと、後から変更することができないのでしょうかといったご相談もよくあります。
養育費の支払いは長期間に及びますから、その後、家庭環境や職場環境のほか、収入状況等が変化することがあります。環境変化の内容によっては、支払うべき養育費の額が変化することもあるので、環境変化の度に、適正な支払額かどうか確認することをおすすめします。
支払い額が変化する主な場合としては、年収の変化、失業、再婚、出産があります。
例えば、元妻が親権者となり元夫が養育費を支払っていたところ、元妻が再婚して、再婚相手がお子さんと養子縁組をすることがあります。この場合、再婚相手がお子さんの第一支払義務者とされます。したがって、元夫には養育費の支払義務がなくなります。
養育費が支払われない場合
養育費の支払を約束してもらったといっても、すぐに支払われなくなるだろうというご相談も非常に多くあります。実際に、養育費の支払を止めてしまう方も多いようです。
しかし、我々弁護士からすると、きちんとした手続を踏んでおけば、養育費は、確実に支払ってもらえる可能性の高い費用です。
これは、養育費の支払いが止まってしまった場合には、強制執行ができるからで、しかも法律上強く保護されているからです。強制執行というのは、慰謝料や養育費などが支払われなくなった場合に、強制的に相手の財産を差し押さえ、支払いを実行させる法律上の手続です。
ここで是非とも注意して頂きたい点は、養育費の支払に関する合意は、口約束では足りず、離婚合意書等を作成するのでも足りないということです。強制執行が可能となるのは、調停や訴訟で決められた場合や公正証書が作成されている場合に限られています。ですから、お子さんがまだ小さいケースこそ、調停などで養育費をきちんと取り決めておく必要が高いのです。
では、実際に強制執行をするには、どうしたら良いのでしょうか。
これは、裁判所に強制執行の申立てをすることとなります。手続としてそれほど難しいわけではありません。
注意しておきたい点は、申し立てる妻側が、強制執行の対象を特定しなければならないということです。強制執行の対象は、給与が最も典型です。夫の勤務先さえ把握しておけば、養育費の金額について給与から強制的に支払がされることとなります。給与の次に典型的なものは、夫の預貯金です。どの銀行に預貯金があるのかといったことは是非とも把握しておきたい事柄です。
先ほど、養育費は法律上強く保護されていると書きましたが、ここではその理由をご説明します。
一般に、給与の強制執行の対象範囲は、手取りの1/4までです。
しかし、養育費の場合は、権利者の生活がかかっているので、手取りのうち1/2まで強制執行の対象となります。つまり、手取り給与の半分を強制執行で回収できるのです。しかも、会社から、養育費を直接支払ってもらうこととなります。したがって、離婚した後も、元夫がどこの会社に勤めているかを把握しておくことが極めて重要となります。